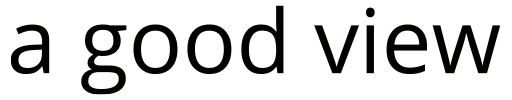自宅や会社、店舗に植物を飾ることが一般的になったのはいつからでしょう?
今や当たり前すぎて、いつからなんて意識することすらありませんね。
でも、空間に植物を取り入れる習慣が広まったのには、いくつかの理由があります。
植物の心理的・生理的効果
植物には、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらすことが科学的に証明されています。例えば、1989年にNASAが発表した研究では、植物が空気中の有害物質を除去する働きを持つことが示されました※1。また、オフィス環境に植物を取り入れることで、従業員の生産性が向上するという研究結果もあります※2。
空間のデザイン性向上
植物はインテリアの一部としても重宝され、無機質な空間に温かみを加えたり、空間のアクセントとなる役割を果たします。特に、北欧やジャパンディスタイル(日本と北欧のミックス)のインテリアでは、自然素材との調和を意識したデザインが好まれ、植物が重要な要素となっています。
ライフスタイルの変化
都市化が進むにつれて、日常的に自然と触れ合う機会が減少しました。そのため、室内に植物を取り入れることで、自然とのつながりを求める人が増えているとも考えられます。
植物が屋内に普及した歴史
植物を屋内に飾る習慣は古くから存在しますが、一般に広く普及し、当たり前の存在となったのはいくつかの段階を経てのことです。
・古代から17世紀:富裕層の嗜み
古代エジプトやギリシャ、ローマでは、既に富裕層が鉢植えの植物を屋内で楽しんでいました。中国でも盆栽文化のように古くから室内で植物を育てる習慣があります。17世紀の大航海時代には、ヨーロッパに珍しい異国の植物が持ち込まれ、貴族や裕福な人々の間で熱帯植物への関心が高まりました。
・19世紀(ヴィクトリア朝時代):一般家庭への普及の兆し
室内植物の普及に最も大きな影響を与えたのは、19世紀のヴィクトリア朝時代です。暖房技術の進歩やガラス製造の発展により、ガラス温室(ワーディアンケースなど)が普及し、繊細な熱帯植物を屋内で育てることが容易になりました。この時代には、中流階級の間でも室内植物がステータスシンボルとして広く受け入れられ、ヤシやシダなどが人気を博しました。
・20世紀以降:より身近な存在へ
第二次世界大戦後、オフィス環境に手入れのしやすい植物が導入され始めました。特に1970年代には、手軽に育てられる品種が普及し、マクラメのプラントハンガーなどと共に、家庭で日常的に植物を飾るブームが到来。より多くの人々にとって室内植物が身近な存在となっていきました。
・現代:ライフスタイルの一部に
近年では、パンデミックによる在宅時間の増加や、自然とのつながりを求める意識の高まり、SNSを通じた「ボタニカルライフ」の流行などにより、植物を自宅やオフィス、店舗に飾ることがさらに一般的で当たり前のこととなっています。
では、本物の植物でなくても、例えば植物画でも同様の効果が期待できるのでしょうか?
これについては、完全に同じ効果とは言えませんが、心理的なリラックス効果や空間の印象を変える力は十分にあります。
視覚的な癒し
植物の画像や絵を見ることによって、自然を連想し、リラックスできることが研究で示されています※3。実際、医療施設やオフィスの壁に自然の風景画を飾ることで、ストレスが軽減されたという調査結果も多数ありますし、わたし自身が実感しています。
かのナイチンゲールも著作『看護覚え書』のなかで「環境が患者の回復に与える影響」について述べており、特に 「光、空気、静けさ、そして美しい景色」が重要であることを強調しています。彼女は、病室の窓からの眺めや、壁にかけられた絵などの視覚的要素が患者の精神状態に影響を与え、回復を助けると指摘しています※4。
インテリアとしての調和
植物の絵は、生花や観葉植物と違い、手入れ不要でありながら、ナチュラルな雰囲気を演出できます。特に、水彩画やボタニカルアートは、シンプルな空間にも馴染みやすく、上品なアクセントとして機能します。
ほとんどの方が、細かいことを除けば「知ってたよ」と仰る内容かもしれません。でも、なんとなく感じていたことが、実際の研究や実験によって裏付けられていると知ると、あらためて納得させられますね。本物の植物も、植物画(ボタニカルアート)も、日々の暮らしの中でその静かな力を発揮してくれます。それぞれの方法で「自分らしい空間」をつくる楽しみを、ぜひ見つけてみてください。
当店にも植物が描かれた作品が複数ありますので、是非ご覧ください。
植物画 https://agoodview.jp/collections/botanical
※1. 著者:Wolverton, B. C., et al.
NASAが行った研究で、室内植物が空気中の有害物質(ベンゼン、ホルムアルデヒドなど)を10~70%除去する能力を持つことを示しています。しかし、この実験は密閉環境で行われたものなので、一般的な生活空間で同様の効果を得るには、かなりの数の植物が必要とされる可能性があります。
※2. 著者:Bringslimark, T., et al.
オフィス環境における観葉植物の心理的効果を調査し、2007年にストレス軽減や生産性向上に寄与する可能性があることを示唆しました。
※3.著者: Kaplan, R. & Kaplan, S.
自然環境が人間の認知や心理に与える影響を研究し1989年に発表。自然を見ることによるストレス軽減や注意回復効果(Attention Restoration Theory)を提唱しています。
※4. 著者:Florence Nightingale.
フローレンス・ナイチンゲールが1860年に執筆した、近代看護の基礎を築いた書籍です。単なる技術的なマニュアルではなく、「病人の回復を助けるために看護師がすべきこと」をまとめた実践的な指南書です。