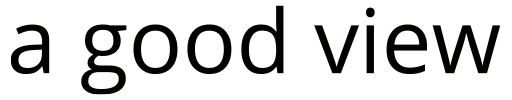「静物画」と聞くと、「動かないモノの絵」といった印象を持つ方が多いのではないでしょうか。実は、それで正解です。意外とシンプルでしたね(笑)。
英語では「スティルライフ(Still Life)」と呼ばれ、「静かな生命」や「動かぬ存在の美しさ」を表現した絵画ジャンルとして知られています。
ところで、静物画と似たテーマの作品として、「植物画」や「室内画」もあります。名前は似ていても、そこにはそれぞれ異なる視点や役割があるのです。ここでは、これら3つのジャンルのちがいについてご紹介していきます。

左から「静物画」>「植物画」>「室内画」 いずれもAIで作成
1. 静物画と植物画の違い
静物画には、花や果物といった植物がよく登場します。そのため、植物画(ボタニカルアート)と混同されることもありますが、両者には明確な違いがあります。
植物画は、植物の形や構造を細かく描写し、学術的な記録や観察の成果としての役割が強いもの。一方、静物画は、構図や光、質感、そしてそこに込められた意味など、芸術としての表現に重きが置かれます。
たとえば、17世紀オランダの静物画では、花瓶に活けた花や熟した果物がよく描かれました。ただし、それらは単なる“記録”ではなく、花の枯れゆく姿に人生の儚さを重ねるなど、象徴的な意味が込められていたりもします。
では、ゴッホの《ひまわり》はどちらでしょうか? じつは、一般的には静物画として分類されます。描かれているのは植物ですが、その目的が「観察記録」ではなく、感情や表現を追求する芸術作品だからです。

2. 静物画と室内画の違い
つづいて、静物画と室内画のちがいについて。
どちらも室内を舞台にしているため、共通点が多いように感じられます。ですが、室内画(インテリア・ペインティング)は、空間そのものを描くことが主な目的です。家具の配置や光の入り方、人の気配を感じさせる構図など、暮らしの“場”の雰囲気を伝えようとします。
一方で静物画は、特定のモノに視点をぐっと寄せて、その存在の美しさや象徴性を描くことが特徴です。小さな物体に宿る時間や空気、物語に耳を澄ますような感覚と言ってもいいかもしれません。

画像は栗原あきさんの「VENTILATION(ヴェンティレーション)フレーム50」
植物画は科学的なまなざしで、室内画は暮らしの空気感を、そして静物画は、そこにある“モノ”の存在そのものを見つめる絵。
違いを知って眺めると、今まで見過ごしていた作品の表情や意味が、不意に心に届くこともあるでしょう。
ちなみに当店では、分類としては静物画にあたる作品でも、植物が主役であれば植物画としても掲載しています。カテゴリーはあくまで検索のためのものであって、楽しみ方を制限するものではありません。
あまりジャンルにとらわれすぎず、いろいろな作品を自由に眺めてみてください。
あなたにとっての「ビビッとくる一枚」と出会えますように。
a good view の
静物画はこちら https://agoodview.jp/collections/still-life